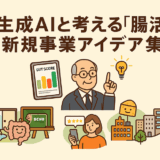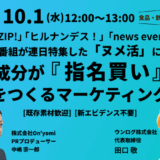腸活に関する直近1ヶ月の最新情報を抜粋してご紹介します。 腸活ブランド担当者の方のキャッチアップのお役に立てますと幸いです。
■ 腸活関連ニュースクリップ(2025年8月)
腸活×健康トレンド
- タイトル:老化も病気も対策は腸がポイントだった… 医師が教える「体をサビさせない」新腸活
- 要約:順天堂大学・小林弘幸氏が、腸内環境の悪化が全身に及ぼす影響と“抗酸化×腸活”の考え方を整理。日常で取り入れやすい腸活ルーティンを提案し、美容・疲労・体調安定まで含む“腸を起点にした予防”をわかりやすく紹介。
- URL:https://toyokeizai.net/articles/-/893568
メディア露出の大きい専門家発信で「腸活=美容やメンタル安定にも効く」が再確認されました。機能訴求だけでなく“続けやすい小さな習慣”をセットで提示できるブランドが、生活者の定着を獲得しやすい局面です。
- タイトル: カルビー×メタジェンが共同研究で、個人の腸内環境に合ったプレバイオティクスグラノーラで気分の改善効果を確認
- 要約: カルビーとメタジェンによる共同研究で、個人の腸内環境タイプに合わせたプレバイオティクスを摂取することで、腸内での短鎖脂肪酸の増加と、気分の改善効果が初めて確認された。これは「腸脳相関」の応用研究として注目される 。
- URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001645.000030525.html
この研究は、腸活が「便通改善」や「免疫力」といった従来の領域から、さらに一歩進んで「メンタルヘルス」という領域に深く関与していることを示唆しています 。特に重要なのは、画一的なプレバイオティクスではなく、「個人のタイプ」に合わせた摂取がより効果的であることが科学的に裏付けられた点です。
海外トレンド情報
- タイトル:ウォーターケフィアが“次の腸活ドリンク”候補に
- 要約:欧州メディアが、低酸味・ソフトな発泡感の“ウォーターケフィア”を新たな成長ドライバーとして特集。2025–2030年に年平均8.72%成長予測が挙がるなど、市場ポテンシャルが注目されています。
- URL:https://www.foodnavigator.com/Article/2025/08/18/water-kefir-could-be-next-gut-health-growth-driver/
コンブチャに続く“飲むプロバイオティクス”の候補。日本では受け入れやすい風味設計と衛生管理スキームが鍵。先行してプロトタイプ・試飲導入で文脈を作る価値があります。
腸活の最新研究
- タイトル:舌下免疫療法で腸内細菌が変わる可能性—東北大ほか国際共同研究
- 要約:花粉症の舌下免疫療法(SLIT)により腸内微生物叢が変化し得ることを示唆。口腔免疫と腸内環境の連関という新しい視点で、全身の免疫調整と腸内の関係が一歩前進。
- URL:https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2025/08/press20250807-02-sublingually.html
口腔—腸—免疫の多層連結は、食品×オーラルケア連動の新テーマ。アレルギー季節商戦とも相性がよく、機能性食品+日常ケアの複合提案に拡張余地があります。
生活者の腸活に関するトレンド調査・データ
- タイトル:腸活への関心は高いのに続かない—“挫折ポイント”が可視化
- 要約:FNNの生活者調査特集では、「腸活に興味はあるが続かない」が8割近い印象として浮上。何をすべきか不明・手間・味(続けにくさ)が障壁に。
- URL:https://www.fnn.jp/articles/-/908750
勝ち筋は“決める負担を減らす”。“朝これだけ”“夜これだけ”など意思決定コストを下げた商品体験、アプリやSNSでのデイリー伴走がLTVを押し上げます。
新技術・素材開発に関する最新情報
- タイトル:産総研「魚の新腸活時代」—魚の腸から世界初の“酪酸産生菌”を発見
- 要約:ニジマス腸内から、至適温度20℃前後の新属新種・酪酸産生菌を同定。水産養殖における“魚には魚の酪酸産生菌”という発想で、定着性や魚病抑制など実装が期待。
- URL:https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250806/pr20250806.html
ヒト以外の腸活テクノロジー進展はフードテック×サステナビリティ文脈と接続。副産物や飼料・ペット領域まで波及し、機能性原料調達や共創の新ルートになり得ます。
異業種・他ジャンルとのコラボ
- タイトル: 『あすけん』と映画『8番出口』がコラボ:「出口の見えないダイエットループからの脱出」キャンペーンを開催
- 要約: AI食事管理アプリ「あすけん」が、公開予定の映画『8番出口』とコラボレーションを実施。映画のコンセプトとアプリのテーマを重ね合わせ、SNSキャンペーンを通じてダイエットの継続をサポートする 。
- URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000058653.html
直接的な腸活コラボではありませんが、この事例はウェルネス分野における異業種コラボの可能性を示唆しています 。企業は、自社のブランドイメージや製品機能と親和性のある異業種のコンテンツやサービスと連携することで、ターゲット層を拡大し、ブランドの新たな価値を創造できるでしょう。
今後注目される腸活関連の素材やキーワード
- タイトル:レジスタントスターチ再注目—“冷やご飯”など身近な実践法が拡散
- 要約:専門家解説をもとに、冷やご飯・玄米・冷やし焼き芋などで摂れる“レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)”がメディアで話題に。腸内細菌のエサとしての機能に再注目。
- URL:https://news.livedoor.com/article/detail/29401449/
高価格素材に頼らず“家庭で再現できる腸活”を示せるキーワード。商品側は“冷やすだけでRSアップ”など調理・保管のひと工夫まで提案すると、レシピ連動の購買喚起が狙えます。
まとめ
今月は「続けやすさ」と「新しい飲用体験」の二極で腸活が進みました。国内では専門家発信とメディア特集が“サビない腸活”“挫折しない腸活”を後押しし、“これだけ/ゆるっと”の設計が生活者の共感を獲得。一方、海外ではウォーターケフィアやプロバイオティクス入りコーヒーなど、“飲む×機能”の次世代フォーマットが動き出しています。研究面では口腔—腸—免疫の連結や、水産分野の酪酸産生菌など応用領域が広がり、腸活は“人の内側”を越えて産業と体験の設計思想へ。
食品メーカーにとっては、
(1) 意思決定コストを下げるUX(“朝これだけ”など)
(2) シーン内実装(スポーツ・観光・職域カフェ等でのトライアル)
(3) 調理や保管の一工夫まで含めた提案(RSなど)
(4) 法対応とエビデンス運用の一体化の4点が有効です。
プロダクト起点にとどまらず、日常の小さな成功体験を積ませる設計こそが、腸活カテゴリーの継続率とLTVを押し上げる最短ルートと考えます。
最新情報をメールでお届けします
腸活に関する直近1ヶ月の最新情報を抜粋してご紹介します。 腸活ブランド担当者の方のキャッチアップのお役に立てますと幸いです。
メールマガジン登録はこちら